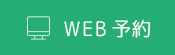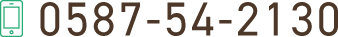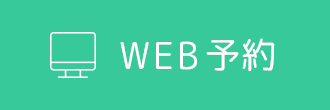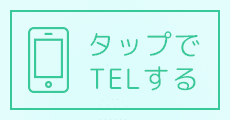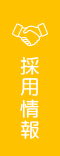開咬になる主な原因と放置するリスクについて
 皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。本日は「開咬(かいこう)」についてお話しします。開咬は、見た目だけでなく、噛み合わせや発音、さらには歯茎や顎関節の健康にも影響を及ぼすことがあります。開咬の原因や放置するリスクを正しく理解し、早めに対処することが大切です。
皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。本日は「開咬(かいこう)」についてお話しします。開咬は、見た目だけでなく、噛み合わせや発音、さらには歯茎や顎関節の健康にも影響を及ぼすことがあります。開咬の原因や放置するリスクを正しく理解し、早めに対処することが大切です。
このコラムでは、開咬の定義や主な原因、放置することで生じるリスク、さらに治療方法について詳しく解説していきます。お子さんの噛み合わせが気になる方や、自分の歯の状態に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも開咬とは?
開咬(かいこう)とは、上下の歯が正常に噛み合わず、歯と歯の間に隙間ができる噛み合わせの不正の一種です。この状態は特に前歯で見られることが多く、笑ったときに隙間が目立つことがあります。また、奥歯だけが接触していて、前歯が全く噛み合わないケースも開咬に含まれます。
開咬は機能面だけでなく審美面にも影響を及ぼします。具体的には、食べ物をうまく噛み切れなかったり、発音が不明瞭になったりすることがあります。例えば、「サ行」や「タ行」の発音が難しくなることが一般的です。このような状態を放置すると、さらに悪化する可能性があるため、早期の診断と治療が重要です。
開咬になる原因
開咬の原因にはさまざまな要因が関与しています。以下に主な原因を挙げてみましょう。
遺伝的要因
開咬は、骨格的な要因によって生じる場合があります。例えば、上下の顎の成長バランスが悪いと、歯が正常に噛み合わなくなることがあります。
口腔習癖
お子さんによく見られる指しゃぶりや舌を前に突き出す癖(舌癖)は、開咬の主要な原因となります。これらの癖が長期間続くと、歯列や顎の発育に影響を与えます。
歯並びの問題
乳歯の抜け方や生え変わりのタイミングがずれると、永久歯の位置が乱れることがあります。これが結果的に開咬につながることもあります。
開咬を放置するリスク
開咬をそのままにしておくと、次のようなリスクが生じます。
噛む力の低下
歯が正常に噛み合わないため、食べ物を十分に噛むことができず、消化器官に負担がかかることがあります。また、食事の満足感が得られない場合もあります。
発音障害
開咬によって舌の位置が不安定になるため、特定の音が発音しにくくなります。これにより、コミュニケーションに支障をきたす場合があります。
顎関節症のリスク
開咬は顎関節にも影響を及ぼします。顎関節に過度な負担がかかると、顎関節症を引き起こすことがあり、痛みや開口障害の原因となります。
心理的影響
開咬は見た目にも影響を及ぼすため、特に思春期のお子さんにとっては自己肯定感を低下させる要因となることがあります。
開咬を治す方法
開咬の治療は、原因や程度に応じてさまざまな方法があります。
矯正治療
開咬の治療として一般的なのが矯正治療です。特に成長期のお子さんの場合、顎の成長をコントロールする装置や、舌の位置を改善するトレーナーを使用することがあります。成人の場合は、歯列矯正器具を用いて歯の位置を整える治療が行われます。
習癖の改善
指しゃぶりや舌癖などの習癖が原因の場合、それらを改善するためのトレーニングや、場合によっては専門家による指導が必要です。
外科的治療
骨格的な問題が大きい場合は、外科的手術が検討されることもあります。この場合、矯正治療と併用することで、より良い結果が得られます。
口腔筋機能療法(MFT)
舌や唇、頬の筋肉を正しく使うためのトレーニングを行う療法です。これにより、舌癖の改善や口腔周囲筋のバランスを整えることが期待できます。
まとめ
 開咬は、噛み合わせや発音、さらには歯や顎関節の健康にも影響を及ぼす問題です。その原因は遺伝的要因から生活習慣まで多岐にわたり、放置することでさまざまなリスクを招く可能性があります。しかし、矯正治療や習癖の改善、口腔筋機能療法などの適切な治療を行うことで、改善が期待できます。
開咬は、噛み合わせや発音、さらには歯や顎関節の健康にも影響を及ぼす問題です。その原因は遺伝的要因から生活習慣まで多岐にわたり、放置することでさまざまなリスクを招く可能性があります。しかし、矯正治療や習癖の改善、口腔筋機能療法などの適切な治療を行うことで、改善が期待できます。
お子さんの噛み合わせが気になる場合や、自分の歯並びに不安がある方は、ぜひ早めに歯科医院で相談してください。つかもと歯科では、患者さん一人ひとりに合った治療方法を提案し、健康な噛み合わせをサポートします。お気軽にご相談ください。